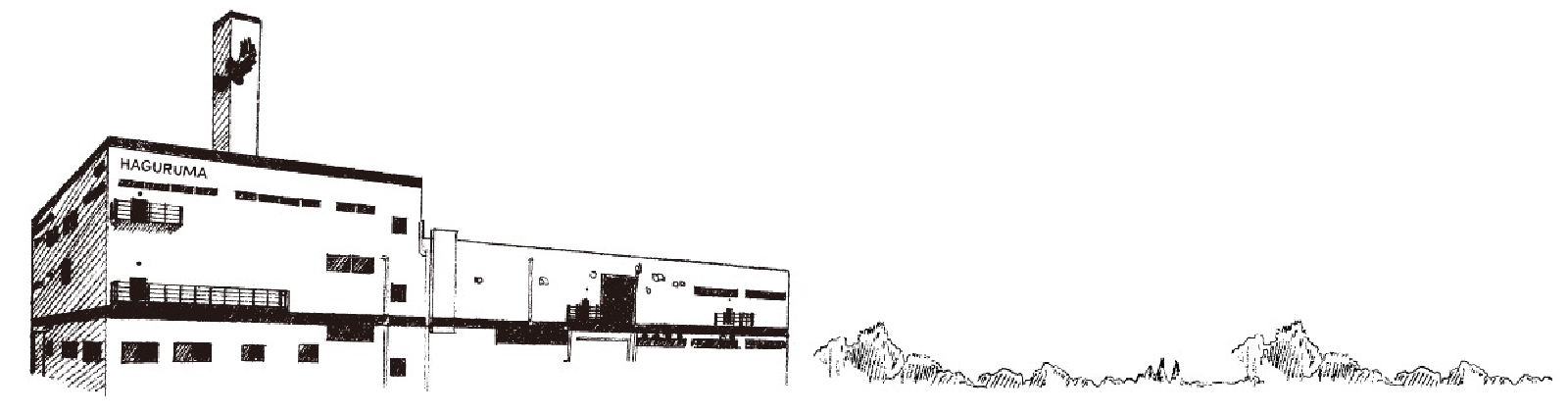【前編】色鮮やかな塗り絵の世界~歴史と文化を辿る~
2025/07/15
大人から子どもまで、多くの人に愛されている「塗り絵」。自由に色付けできるため、同じデザインでも塗る人によって異なる作品に見えるところも魅力です。2013年には、『Secret Garden(邦題 秘密の花園)』というイギリス生まれの塗り絵集が日本に初上陸し、「大人向けの塗り絵」ブームも巻き起こしています。今回は、そんな塗り絵の歴史と文化に焦点を当てて見ていきましょう。

まず、日本において塗り絵の起源となるものが発見されたのは江戸時代だと言われています。当時の本の挿絵に、色が塗られていたものが見つかっているそうです。塗り方も、拙いものから枠に沿って正確に塗ったものまで幅広く存在しており、子どもから大人まで色付けを楽しんでいたことが想像できます。また、この線画に色を付ける行為に対して、有識者の中には「浮世絵の流行が影響しているのかもしれない」と考える人もいるようです。
その後、明治時代(1868年~)に入ると「塗り絵」が登場します。徳川幕府が終わり、権力が朝廷へと移った明治時代。「明治維新」という大きな社会改革が起こり、欧米の文化や制度も積極的に取り入れられました。塗り絵も、ヨーロッパの鉛筆画が当時の図画教育の絵手本として使用されたのがきっかけだと言われています。当時の教科書には外国の風景や人が掲載されており、その点から文明開化の最中(さなか)であったことも感じられるでしょう。ちなみに明治前期は、小学校では「罫画(けいが)」、中学校では「画学」という名前で図画教育の授業がおこなわれたそうです。またこの授業は、実利的な説明図を描けるようになる訓練を目的としていました。しかしこの授業内容に対して、「子どもたちの、個性や創造性を重視する教育には向いていないのでは?」と疑念を抱く人は次第に増え、大正時代後期に入ると転換期を迎えます。版画家・洋画家である「山本鼎(やまもと・かなえ)」が、「児童自由画の奨励」に関する講演をおこなったことにより、図画教育の自由な作風を推進する「自由画教育運動」が始まったのです。その後、大正デモクラシーが追い風となり、賛同者は増加し運動は全国に拡大。その結果、自由教育は昭和初期まで図画教育の基盤となりました。

このように教育分野の中で広がりを見せた塗り絵ですが、次第にその枠組みも超えていきます。明治後期になると懸賞としての塗り絵の応募が流行し、大正時代(1912年~)には塗り絵帖も発売されました。教育という範囲から抜け出し「娯楽」や「遊び」として受け入れられ、少しずつ人々の生活に馴染んでいったのです。とはいえ、好意的な人ばかりではなかったようで、絵画の専門家からは「創意工夫の喪失」や「型の強制」など批判があったとも記録されています。
そして、大正を過ぎ時代は昭和(1926年~)へと移ります。この時代は、塗り絵作家・蔦屋喜一(つたや・きいち)氏の「きいちのぬりえ」が一世を風靡しました。特に女子からの人気が強く、当時の少女たちが描いていた夢や憧れを具現化しているところ。加えて、見ると当時のファッションや生活様式などを思い出すところなどが理由だと言われています。また「きいちのぬりえ」に限らず、当時の流行を取り入れ小道具まで丁寧に描かれた塗り絵は、女子たちの心を掴み離さなかったようです。この塗り絵ブームは、1940年〜1960年代まで続きました。そして、時代が平成に近づくにつれアニメやおもちゃが発展し、塗り絵の人気もゆるやかに落ち着いていきます。とはいえ最盛期ほどの活気はないものの、その後も一定の人々に根強く愛されたようです。
平成になると、塗り絵は「大人の塗り絵ブーム」により再び脚光を浴びます。ひとつ目は、認知症予防のためという理由から、高齢者を中心に再度注目されました。ふたつ目は、記事の冒頭でも少し触れた、イギリスの塗り絵『ひみつの花園』の日本上陸です。花や庭、動物などが緻密に描かれており、これまでの塗り絵とは異なる魅力があるとして世界中のファンを魅了しました。これらのシリーズは、令和の今も高い人気を誇っています。大人向けの美しい塗り絵は各出版社から出ていますので、気になる方は書店やネットで探してみてください。

教材や娯楽など、各時代のニーズに寄り添い現代まで愛され続けている「塗り絵」。何かと忙しい現代において、静かに線画と向き合い色を付けていく作業は、あなたの心を落ち着かせてくれるかもしれません。そのような面も含めて、後編となる次回はデザインや紙素材などに注目してみようと思います。
文・鶴田有紀
--------------------------------------------------
〈参考文献〉
・“大人向けの塗り絵” ブームの火付け役『ひみつの花園』日本発売10周年を記念して、グラフィック社「大人のぬりえ10周年フェア」を全国書店で順次開催中!|PRTIMES
・応募者は4歳から106歳まで! 他に類を見ない全世代参加の人気コンテスト 第11回大人の塗り絵コンテスト展覧会 4月1日から開催|PRTIMES
・蔦谷喜一(つたや きいち)について|ぬりえ美術館
・「ぬりえほん」の展望に関する基礎的考察|田邉 夏子 伊藤 真市
・第1期 近代地方行政の黎明期(1868-1880年)|立命館大学政策科学部教授 上子 秋生
・近代日本の教科書の歩み 図画・工作教科書|秋元幸茂 著
・塗り絵と色彩教育に関する一考察|小川直茂









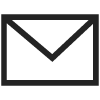 info@haguruma.co.jp
info@haguruma.co.jp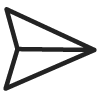 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム