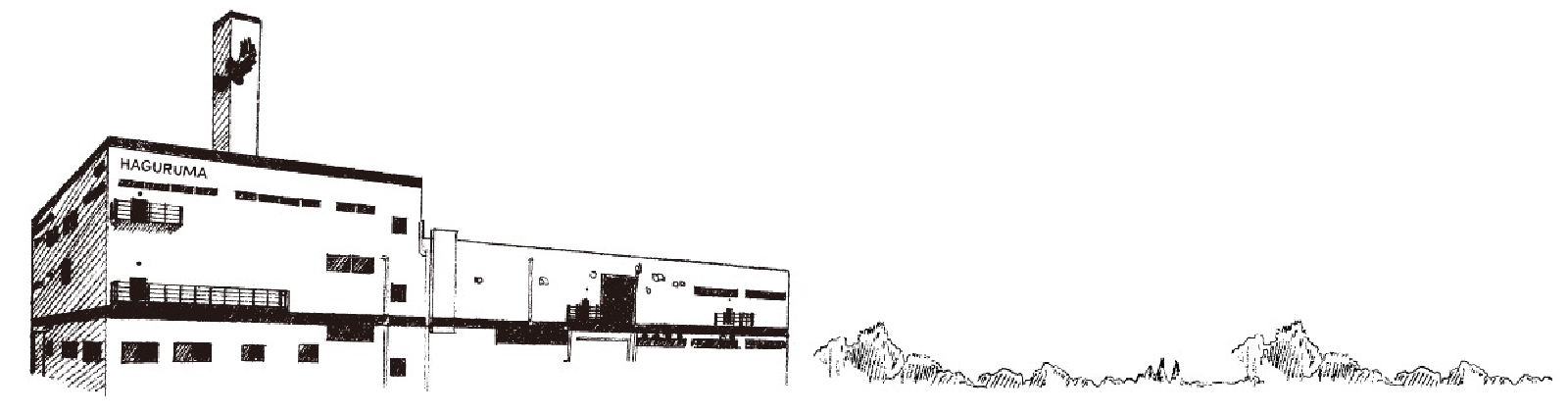【前編】美しい旋律を生みだす音の地図~邦楽と洋楽に用いられる楽譜の歴史を辿る~
2025/09/30
さまざまな音を組み合わせ、美しい旋律を生みだす楽譜。ピアノやバイオリンなど、普段から楽器に触れている人にとっては馴染みの深いアイテムではないでしょうか。近頃はデジタルに移行する人もいますが、手触りや見た目を理由に紙の楽譜を好む人もまだまだ多い印象を受けます。そこで今回は、奏者たちにとって大切なアイテムのひとつである「楽譜」の世界を覗いてみましょう。前編となる本記事では「邦楽(日本)」と「洋楽(世界)」、それぞれの楽譜の歴史にスポットを当てます。

まずは「邦楽(ほうがく)」、いわゆる和楽器を奏でる際に用いられる楽譜の歴史をご紹介します。尺八や三味線、箏(こと)、琵琶などの楽譜は、江戸時代前期には存在していたと記録されています。しかし、当時の邦楽の習得方法は「口伝え」という、楽器の音を「ちんとんしゃん」や「とっちりちん」「ぴーひょろ」など、擬音語で表現した歌を覚えることが一般的でした。そのため、楽譜は覚え書き(メモ)程度の位置づけであったそうです。なぜ、口伝えでの習得が浸透していたのかというと、箏や琵琶などの奏者に盲人が多かったこと。そして、それぞれの曲を師から弟子へ受け継ぐ行為が秘伝化していたなどの背景が影響しているようです。確かに、目の見えない人は音で覚えるほかありませんし、代々受け継がれる曲を楽譜として残してしまうと、流派以外の人に知られる恐れもあります。
また邦楽は、西洋音楽のように、必ずしも楽譜通り演奏することが求められるわけではないという点も大きいでしょう。大人数が集まりひとつの曲を演奏することも、当時は想定していませんでした。このような多様な理由から、楽譜ではなく口伝えが好まれていたのです。しかし明治20年代になると、日本でも西洋音楽が本格的に受け入れられはじめます。それに伴い、楽譜の共有や必要性が認識されはじめました。さらに明治30年代には、バイオリンなどの洋楽器で邦楽曲を演奏するというユニークな動きもあり、「邦楽曲の洋楽譜」なるものも登場します。
その後も、明治時代末期から五線譜に書かれた邦楽曲が登場しますが、受け継がれてきた練習法が失われなかったことや、五線譜では邦楽を完全に表現しきれないなどを理由に、邦楽曲が五線譜へ完全に移ることはなかったそうです。とはいえ、明治はレコード、昭和にはラジオや映画が登場し、関連曲の楽譜出版は加速。邦楽以外の分野では、楽譜出版の勢いが増していきました。

画像:雅楽器の「笙(しょう)」と、その楽譜
続いては、世界の楽譜の歴史について見ていきましょう。楽譜のもととなるものが誕生したのは紀元前2世紀頃だといわれており、当時は文字や記号などが記された「文字譜(もじふ)」を使用していました。その後中世(諸説あるが、日本でいう鎌倉時代~室町時代)になると、音楽の目的や形式が多様化しはじめ「ネウマ譜」が登場します。このネウマ譜は、現代でも馴染みの深い「五線譜」の祖先といわれています。最初は1本の線から始まり、音の高さを明確にしようとする動きが強まるにつれ線の数は増えていき、最終的に5本になったそうです。とはいえ、17世紀以降も5線以外の楽譜も用いられました。
音の高さを明確にするネウマ譜の誕生後、人々は「音の長さ」も分かるようにしたいと思い始めます。そのような背景もあり、13世紀半ばになると音の長さを形状の異なる音符で表現する「定量記譜法」を用いた楽譜も登場しました。ちなみに当時の楽譜には、羊の皮をなめした「羊皮紙」が使用されており、譜線を引く人やインクを使用し楽譜に刻み込む人などにより分業制で作られていたそうです。そのため、手間がかかるがゆえにとても高価でした。しかし15世紀半ばになると、紙の普及に伴い楽譜も羊皮紙から紙に移り変わります。
また15世紀は、声楽曲のほかに、器楽曲の楽譜が初めて見つかった時代でもあります。器楽曲自体は、以前から存在していました。しかし、器楽曲の楽譜は教会の圧力により残せないことに加えて、当時は楽譜に記す技術を教会関係者しか知らなかったそうです。そのような理由から、教会が衰退する15世紀後半まで器楽曲の楽譜は残されていませんでした。その後も時代とともに変化していき、現代の形に近い「五線譜」になったのは19世紀のことだといわれています。
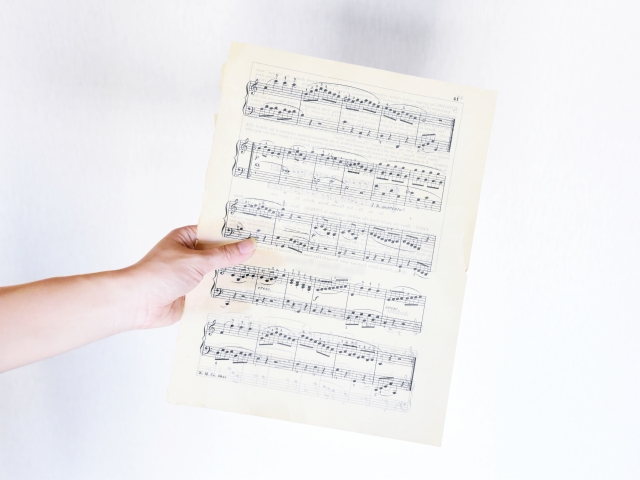
美しい旋律を繰り返し奏でられるよう、目に見える形で残すための楽譜。今回は、日本(邦楽)と世界(洋楽)の歴史に光を当ててご紹介しました。気になる方は、邦楽と洋楽の楽譜を見比べてみてください。それぞれの性質に合わせて変化を遂げた楽譜を見て、新たな発見があるかもしれません。そして後編となる次回は、楽譜の素材や種類などに注目していきます。
文・鶴田有紀
--------------------------------------------------
〈参考文献〉
・邦楽の楽譜~歌う楽譜、見る楽譜~|文書館レキシノオト
https://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/archivesexhibition/AW13%20rekishinooto/30.pdf
・楽譜の風景‐音楽の明治・大正・昭和‐|国立国会図書館月報
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8235961_po_geppo130708.pdf?contentNo=1
・楽譜の歴史|株式会社 カマクラムジカ
http://www.kamakura-musica.com/html/page7.html
・音楽教育の基礎研究としての音律や楽譜の研究 |千葉大学大学院教育学研究科研究生 藤田朋世 著
https://ace-npo.org/fujikawa-lab/file/pdf/bulletin/2012/fujita.pdf









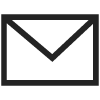 info@haguruma.co.jp
info@haguruma.co.jp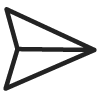 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム